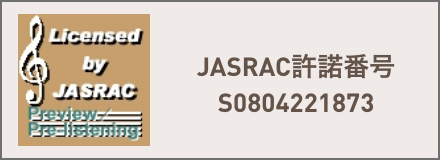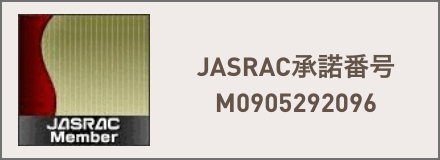【教則楽譜】バンドのためのフレキシブル・コラール集: arr. 後藤洋 [吹奏楽フレキシブル]
・1配送につき税込11,000円以上のご注文で国内送料無料
・コンビニ後払い、クレジットカード、銀行振込利用可
・[在庫あり]は営業日正午までのご注文で即日出荷
・International Shipping
- 編曲: 後藤洋
- 編成:管4+打3
- グレード:2+
ブレーンミュージック/FLMS-87901
- 概要
- 編成/曲目
- 補足
- ENGLISH
【教則楽譜】バンドのためのフレキシブル・コラール集
後藤洋氏総監修の新たなトレーニング!
吹奏楽のサウンド・歌い方の基本的な練習として取り組まれている「コラール」。
後藤洋氏総監修の元、親しみのある世界の唱歌で旋律と和音の基礎が楽しく・徹底的に学べる曲集に仕上がりました!
現場に合わせたフレキシブル編成で書かれているため4重奏のアンサンブルから大編成のバンドまで多くの団体が使えます!
これまであまりなかった短調のコラールやゆったりとした6/8拍子のトレーニングなど、拍子・調整・テンポ等、バリエーション豊かな5作品!
後藤洋氏によるコラールの練習解説付き!
バンド全体が旋律の歌い方を身に着け、ハーモニーの構成が理解できる画期的なコラール集!
4つのコンセプト
1. すべての楽器で旋律の練習を
古くから歌い継がれる旋律から音楽表現を学べます。すべての楽器でメロディの練習をするため、旋律のTuttiが組み込まれています。
2. 基本的な4声の和声を学ぼう
どんな編成にも柔軟に対応する4声のフレキシブル楽譜。旋律を引き立たせる和音の展開を基礎的な4声から学べます
3. 和音をピアノなどで確認
ピアノ譜付きで、ハーモニーディレクターなどを使って簡単に和音確認。和音構成の理解に必須です。
4. 長調だけでなく短調も
長調の作品だけでなくタンチョウの作品も収録。表現とハーモニーを様々な角度から学べます。
コラールを練習する意味とは?
「コラール」は、狭義ではプロテスタント教会の賛美歌を意味します。本来は旋律のみでしたが、16世紀頃には賛美歌の旋律を最上声部に置き、それをシンプルな和声で支えるスタイルの作品が生まれました。今日一般的に親しまれているコラールの多くは、J・S・バッハ(1685-1750)が和声づけを行ったもので、ソプラノ、アルト、テナー、バスの4つの声部を対等にはたらかせて和声の妙を追求したバッハの編曲は、その後のコラールの標準型となりました。今日では、プロテスタントの賛美歌およびその編曲でなくとも、宗教的な雰囲気をそなえ、4つかそれ以上の声部をもつ和声的な楽曲を「コラール」と呼ぶことがあり、特に合唱と吹奏楽の分野では多くの新しいコラールが作曲され続けています。
さて、吹奏楽になぜコラール、またはコラール風の作品が多いのでしょう? いくつか考えられる理由の中で最も重要なのは、吹奏楽が合唱と同様、アンサンブル全体のとけ合った響きをその最大の魅力とする形態だから、ということではないでしょうか。つまり、吹奏楽はコラール風の音楽が得意なのです。そして、コラール風の音楽をとけ合った響きで美しく演奏できることが、すぐれた吹奏楽団の証しなのです。言い換えれば、コラールへの取り組みを通じて美しい響きをつくることは、レベルの高い演奏を目指す上で必須ということになります。
実際、コラールではいくつかの声部が合わさって響きがつくられます。しかも、吹奏楽ではひとつの声部を複数の異なる楽器で重ねるのが一般的です。つまり、異なる楽器をとけ合わせてひとつの声部をつくり、さらにそれらがひとつの大きな合奏の響きとなるのです。そのためには、互いに聴き合い、役割を理解し合い、響きのイメージを共有することが大切になります。これこそ合奏の最も大切な基本と言ってよいでしょう。コラールが吹奏楽の基本的な練習の題材とされている理由が、ここにあります。
しかし、コラールは(そして吹奏楽も)美しい音を単純に並べて終わり、というわけではありません。コラールは音楽、しかも多声音楽です。それぞれの声部には異なる役割があり、時に異なるフレーズをもち、異なる音色やキャラクターも求められます。それらの関係によって、ハーモニーはより深く意味づけられ、より美しく響きます。この、各声部の関係の理解こそ、合奏による音楽表現の基本です。その理解によって、多くの種類の楽器によって奏でられる吹奏楽ならではの、立体的な音楽が出来上がるのです。
コラールは、バランスをとるため、音を合わせるためだけに取り組まれるものではありません。コラールは音楽の基本を勉強するための楽曲でもあるのです。(後藤洋)
■収録作品(編曲:後藤 洋)■
1. さくらさくら (b moll 4/4) 日本古謡
2. 野ばら (Es dur 6/8) 作曲:H.ヴェルナー
3. 荒城の月 (c moll 4/4) 作曲:瀧廉太郎
4. アニー・ローリー (B dur 4/4) 作曲:J.D.スコット
5. 朧月夜 (Es dur 3/4) 作曲:岡野貞一
仕様
- アーティスト
- 編曲: 後藤洋
- 演奏形態
- 吹奏楽
- 編成
- フレキシブル
- グレード
- 2+
- 商品形態
- 教材・教則本( & Part)
- 出版社 / 品番
- ブレーンミュージック / FLMS-87901
- JANコード
- 4995751819994
- 発売日(年)
- 2016/03/25
- キーワード
- 基礎合奏, ,
楽器編成
- 【Part 1】
- Flute
- Oboe
- Clarinet in Eb
- Cornet in Eb
- Clarinet in Bb
- Trumpet in Bb
- Cornet in Bb
- Flugelhorn in Bb
- Alto Saxophone in Eb
- 【Part 2】
- Clarinet in Bb
- Trumpet in Bb
- Cornet in Bb
- Flugelhorn in Bb
- Alto Saxophone in Eb
- Horn in F
- Alto Horn in Eb
- 【Part 3】
- Clarinet in Bb
- Tenor Saxophone in Bb
- Alto Horn in Eb
- Horn in F
- Trombone
- Euphonium
- 【Part 4】
- Bass Clarinet in Bb
- Baritone Saxophone in Eb
- Bassoon
- Trombone
- Euphonium
- Tuba
- String Bass
- ■Percussion
- Snare Drum
- Bass Drum
- Glockenspiel
- Piano score (歌詞)
- サイズ
- 宅急便サイズ
:Arranger: Yo GOTO
Specifications
- ARTIST
- Arranger: Yo GOTO
- INSTRUMENTATION
- Windband
- GRADE
- 2+
- PRODUCT TYPE
- METHOD ( & Part)
- PUBLISHER / Code
- Brain Music / FLMS-87901
- JAN
- 4995751819994
- RELEASE
- 2016/03/25
- OVERSEAS SHIPMENT
- EUROPEAN PARTS
- Not Included

![【教則楽譜】バンドのためのフレキシブル・コラール集: arr. 後藤洋 [吹奏楽フレキシブル]](/html/upload/save_image/104-06367.jpg)